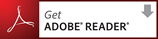- 図解社会経済学 -資本主義とはどのような社会システムか 大谷禎之介著
-

『資本論』への道案内
創意と工夫に溢れた図と、よく練られた構成・懇切な文章で,資本主義社会の偽りの外観を爽快に剥ぎ取っていく経済学入門
「だれでも,現代社会の根幹をなしているのが「資本主義」という社会の仕組みであることを知っている。しかし,あらためて,「資本主義」とはどういうものか,と問われたら,これに答えるのは容易でないことに気づく。じつは,人類史にこの社会システムが登場したときから,この問いに答えようと苦闘してきたのが〈社会経済学〉という,古典派経済学からマルクス経済学にいたる経済学の流れなのである。
…中略…
資本主義とはどのような社会システムか,という問いは,すでに三百歳の齢(よわい)を重ねてきたこの社会が,この先どのような方向に進み,どのように変わり,どのようにして新しい社会を産み落とすのか,という問いでもある。いま,新たな千年紀の入り口に立って,読者とともに人類史の将来に思いを馳せたい。」(著者)A5判/上製/442頁+折込み図5葉
ISBN4-921190-08-9
本体3000円+税
発行
初刷:2001年3月30日
第2刷:2001年4月13日
第3刷:2001年5月25日
第4刷:2002年3月15日
第5刷:2003年4月15日
第6刷:2004年3月15日
第7刷:2004年12月15日
第8刷:2005年5月10日
第9刷:2007年3月1日
第10刷:2008年4月1日
第11刷:2010年3月30日
第12刷:2012年3月30日
第13刷:2014年3月30日
第14刷:2016年3月30日
第15刷:2018年3月30日
- 索引・訂正箇所
-
索引
第14刷までに訂正した箇所
(上記リンクの閲覧には、AdobeReader(AcrobatReader)が必要です。)
AdobeReader(AcrobatReader)がシステムにインストールされていない場合はAdobeサイトから無料でダウンロードが可能です。
Adobeサイトは下記アイコンをクリックして表示してください。※システムにインストールする際は上記アイコンをクリック後に表示されるAdobeサイトで、システム要件・エンドユーザー使用許諾条件などをご確認ください。
- 目次
-
-
- 序章 労働を基礎とする社会把握と経済学の課題
-
第1篇 資本の生産過程
- 第1章 商品と貨幣
- 第2章 資本と剰余価値
- 第3章 労働日の延長と短縮
- 第4章 生産力発展のための諸方法
- 第5章 資本主義的生産関係と労働の疎外
- 第6章 労賃
- 第7章 資本の再生産
- 第8章 資本の蓄積
- 第9章 資本蓄積と相対的過剰人口
- 第10章 資本の本源的蓄積
-
第2篇 資本の流通過程
- 第1章 資本の循環
- 第2章 資本の回転
- 第3章 社会的総資本の再生産と流通
-
第3篇 総過程の諸形態
- 第1章 資本と利潤
- 第2章 平均利潤率と生産価格
- 第3章 利潤率の傾向的低下の法則
- 第4章 商業資本と商業利潤
- 第5章 利子生み資本と利子
- 第6章 土地所有と地代
- おわりに --研究の到達点と残された諸課題--
-
- 図表目次
-
- 図1 労働・生産は人間の生存と社会の存続との基本的条件である
- 図2 生産手段と消費手段,本来の消費と広義の消費
- 図3 使用価値による欲求の充足
- 図4 使用価値取得のための自然への働きかけとしての労働
- 図5 人間によって制御される自然過程としての労働過程
- 図6 労働過程と生産過程
- 図7 労働過程の要素と生産過程の要素
- 図8 生産過程(簡略図)
- 図9 生産力と生産関係
- 図10 生産の特定の社会形態としての歴史的生産様式
- 図11 労働の二つの側面:変形作用+労働力支出
- 図12 具体的労働=有用的労働
- 図13 抽象的労働=人間的労働
- 図14 労働の二重性(簡略図)
- 表1 労働力人口と非労働力人口
- 図15 労働力とその発揮・流動化としての労働
- 図16 生産費用としての労働=抽象的労働の量
- 図17 生産物の生産費用:新労働+旧労働
- 図18 生産費用としての労働(簡略図)
- 図19 同量の抽象的労働でも生産物量は異なりうる
- 図20 具体的労働の生産力の増大は生産費用=抽象的労働の量を減少させる
- 図21 年々の生産物による生産手段と労働力との再生産
- 図22 生産手段と労働力再生産用の消費手段との再生産
- 図23 総生産物は再現生産手段と新生産物とからなる
- 図24 必須生活手段と必須労働
- 図25 剰余労働と剰余生産物
- 図26 再生産の一般的法則(簡略図)
- 図27 労働の生産力の発展による剰余労働の増大
- 図28 社会的総労働の配分と社会的総生産物の分配
- 図29 共同体のもとでの社会的再生産
- 図30 古代的奴隷制のもとでの社会的再生産
- 図31 農奴制のもとでの社会的再生産
- 図32 隷農制のもとでの社会的再生産
- 図33 アソシエーションのもとでの社会的再生産
- 図34 生産様式・社会構成体・社会システム
- 図35 社会形態の発展=生産様式の交替 ⇒巻末折込み
- 図36 社会革命=生産力の発展を起動力とする社会構成体の交替 ⇒巻末折込み
- 図37 分析(現象→本質)と展開(本質→現象)
- 図38 現象と本質の重層的構造
- 図39 下り道と上り道
- 図40 叙述の仕方
- 図41 経済の「循環的流れ」についての常識的イメージ ⇒巻末折込み
- 図42 叙述の出発点と到達点
- 図43 資本主義社会の富は商品という形態をとる
- 図44 商品は使用価値をもっていなければならない
- 図45 商品にとって肝心なのはそれの交換価値である
- 図46 交換価値の大きさを規定しているのは価値である
- 図47 商品の価値は商品に対象化した抽象的労働である
- 図48 労働の二重性
- 図49 労働の二重性が商品の2要因という独自な形態で現われる
- 図50 生産費用としての抽象的労働
- 図51 価値量を規定する労働時間は社会的必要労働時間である(価値規定)
- 図52 労働の生産力が変化すれば商品に対象化した労働の量は変化する
- 図53 熟練度の高い個別的労働は力能の高い労働として意義をもつ
- 図54 複雑労働力の修業費は商品の価値を通じて回収されるほかはない
- 図55 どんな種類の複雑労働も単純労働に還元される
- 図56 商品の価値は社会的必要労働時間によって決まる
- 図57 具体的労働による生産手段の価値の移転
- 図58 労働の二重性と商品の新価値および旧価値
- 図59 最も単純な交換関係
- 図60 交換関係は価値表現を前提する
- 図61 単純な交換関係に含まれている価値表現=価値形態
- 図62 単純な価値形態と個別的等価物
- 図63 全体的な価値形態を含む交換関係
- 図64 全体的な価値形態と多数の特殊的等価物
- 図65 一般的な価値形態を含む交換関係
- 図66 一般的価値形態と一般的等価物
- 図67 貨幣形態と貨幣
- 図68 商品の価格形態
- 図69 価格の貨幣名での表示
- 図70 商品形態は労働生産物の独自な社会的な形態である
- 図71 商品生産関係のもとで,労働生産物は商品となり,貨幣が生まれる
- 図72 アソシエーションにおける社会的労働・社会的取得・社会的所有
- 図73 商品生産における私的労働・私的取得・私的所有
- 図74 商品生産者の生産関係は商品の交換関係をとおして取り結ばれる
- 図75 生産関係の物象化:人びとの関係が諸物象の関係として現われる
- 図76 商品生産では生産関係の物象化と物神崇拝とが必然的に生じる
- 図77 物象の人格化:経済的事象が人格によって代表される
- 図78 商品を生産する労働の矛盾が商品の矛盾として現われる
- 図79 交換過程の矛盾:商品の二つの実現のあいだの矛盾
- 図80 一般的等価物による交換過程の媒介
- 図81 商品の価値表現と商品の価格
- 図82 貨幣の価値尺度機能
- 図83 価値尺度の質
- 図84 商品の価格とそれによって表象されている実在の貨幣
- 図85 貨幣商品の独自な価値表現
- 図86 価格(貨幣)の度量単位としての「円」
- 図87 価格は価値を正確に表現するわけではない
- 図88 商品の変態とその絡みあい
- 図89 1商品の変態における四つの極と3人の登場人物
- 図90 商品流通と流通手段としての貨幣の流通
- 図91 購買手段としての貨幣の機能
- 図92 鋳貨の流通
- 図93 鋳貨の摩滅による実質金量の名目金量からの乖離
- 図94 蓄蔵貨幣の形成(貨幣蓄蔵)
- 図95 現金売買と掛売買
- 図96 掛売買における商品の変態の絡みあいと貨幣の機能
- 図97 掛売買では信用が授受される
- 図98 信用の連鎖と支払手段の流れの連鎖
- 図99 債権と債務との相殺
- 図100 手形流通による債権債務の相殺
- 図101 世界市場における金の運動と世界貨幣の諸機能
- 図102 並行して行なわれる商品変態を媒介する流通手段の量
- 図103 継起的な絡みあった商品変態を媒介する流通手段の量
- 図104 金の生産源から流通部面への金の流入
- 図105 鋳貨準備と蓄蔵貨幣
- 図106 流通貨幣と鋳貨準備とは同じものを別の視点から見たものである
- 図107 流通界から蓄蔵貨幣貯水池への流出とそこからの流入
- 図108 蓄蔵貨幣貯水池その他による流通貨幣量の調節
- 図109 国家紙幣には流通界からの出口がほとんどない
- 図110 流通貨幣量の変動と最低流通必要貨幣量
- 図111 単純な商品流通:W-G-W
- 図112 資本としての貨幣の流通形態:G-W-G
- 図113 資本の一般的定式:G-W-G'
- 図114 資本の謎:価値の増加分はどこから出てくるのか?
- 図115 価値量の変化が生じうる唯一の可能性
- 図116 労働力はそれの消費=労働によって価値を生む
- 図117 資本主義社会では,労働市場で労働力が商品として売買されている
- 図118 時間極めで販売される商品の時間当たりの価格の決まり方
- 図119 労働力の総価値
- 図120 労働力の日価値は,それの総価値と販売日数とによって決まる
- 図121 労働力の総価値と労働力の日価値
- 図122 労働力の再生産費が労働力の価値を規定する
- 図123 労働力の日価値と1労働日が生み出す価値
- 表2 付加価値・賃金・労働分配率(1998年)
- 図124 1労働日が生み出す価値と労働力の日価値との差額は剰余価値である
- 図125 不変資本
- 図126 可変資本
- 図127 価値増殖過程(剰余価値の生産) ⇒巻末折込み
- 図128 生産物価値と価値生産物
- 図129 総生産物の価値の構成部分を表示するさまざまの仕方
- 図130 労働日の諸制限
- 図131 異常に長い労働日は労働力の日価値を激増させる
- 図132 絶対的剰余価値の生産(労働日の延長による剰余価値の増大)
- 図133 相対的剰余価値の生産(必須労働時間の短縮による剰余価値の増大)
- 図134 生産諸条件の相違による特別剰余価値の発生
- 図135 マニュファクチュアの二つの起源
- 図136 異種的マニュファクチュアと有機的マニュファクチュア
- 図137 機械の概念
- 図138 多数の同種機械の協業→機械体系→自動機械体系
- 図139 生産物形成要素としての機械と価値形成要素としての機械
- 図140 賃金の本質:労働力の価値および価格
- 図141 賃金の現象形態:労賃(労働賃金)=労働の価値および価格
- 図142 時間賃金
- 図143 出来高賃金
- 図144 資本主義的生産関係のもとでの社会的再生産
- 図145 資本家階級と労働者階級との取引の外的形態
- 図146 資本家階級と労働者階級との取引の実質的内容
- 図147 資本家は自分の資本価値によって取得した剰余価値を消費する
- 図148 単純再生産の反復によって資本は資本化された剰余価値に転化する
- 図149 蓄積のさいに剰余価値が分解していく諸部分
- 図150 資本の蓄積=剰余価値の資本への転化=資本関係の拡大再生産
- 図151 蓄積の進行によって取得法則が転回する
- 図152 資本の技術的構成と資本の価値構成
- 図153 資本の有機的構成
- 図154 資本の構成の高度化
- 図155 ラサール流の賃金鉄則の考え方
- 図156 資本蓄積が賃金変動を規定するのであって,その逆ではない
- 図157 資本構成の高度化による可変資本の相対的減少
- 図158 一方での労働需要の増加,他方での現役労働者の遊離
- 図159 近代産業の運動形態=産業循環
- 図160 現役労働者軍と産業予備軍
- 図161 資本主義的生産の出発点としての資本蓄積=資本の本源的蓄積
- 図162 労働者と生産手段との分離過程の二つの契機
- 図163 小商品生産者の両極分解
- 図164 小商品生産者のもとでの胚芽的利潤と民富の形成
- 図165 資本・賃労働関係の発生
- 図166 資本の本源的蓄積と個人的所有の再建
- 図167 循環
- 図168 資本の循環
- 図169 貨幣資本の循環の反復は生産資本の循環と商品資本の循環とを含む
- 図170 資本の3形態への空間的分割と資本の3循環の並列的進行
- 図171 流通時間による生産過程(=価値増殖)の中断
- 図172 商品変態の絡みあいと商品流通
- 図173 資本流通の絡みあいと商品流通
- 図174 資本流通と収入流通との絡みあいと商品流通
- 図175 固定資本と流動資本
- 図176 固定資本と流動資本との区別と不変資本と可変資本との区別
- 図177 総資本の回転時間および回転数の算定
- 図178 年剰余価値量と年剰余価値率
- 図179 社会の2大生産部門:生産手段生産部門と消費手段生産部門
- 図180 再生産諸要素の内部補填と相互補填
- 図181 剰余生産物を含む再生産諸要素の内部補填と相互補填
- 図182 マルクスの再生産表式(単純再生産表式)
- 図183 再生産表式の意味
- 図184 再生産表式の説明図(簡略図)
- 図185 単純再生産の法則(3流れの運動)
- 図186 単純再生産の条件
- 図187 貨幣流通による社会的再生産の諸転換の媒介
- 図188 両部門の生産物価値(c+v+m)と価値生産物(v+m)
- 図189 固定資本の償却と更新(償却ファンドの積立と投下)
- 図190 貨幣材料の再生産
- 図191 各部門での資本蓄積=拡大再生産
- 図192 拡大再生産の法則(3流れの運動)
- 図193 拡大再生産の条件
- 図194 拡大再生産の進行過程の一例
- 図195 蓄積ファンドの積立と投下
- 図196 これまで単純再生産が行なわれてきた
- 図197 第Ⅰ部門での蓄積のための配置換え
- 図198 第Ⅱ部門の縮小
- 図199 第Ⅱ部門縮小後の再生産諸要素の補填
- 図200 第2年度から両部門での拡大再生産が可能となる
- 図201 社会的再生産過程における生産・流通・消費の関連 ⇒巻末折込み
- 図202 費用価格および利潤という形態が生み出す諸観念
- 図203 「利潤は流通過程から生まれる」(虚偽の観念)
- 図204 部門内競争によって個別的価値の加重平均である市場価値が成立する
- 図205 資本の有機的構成は生産部門によって異なる
- 図206 資本構成の相違によって剰余価値=利潤の量は異なる
- 図207 資本構成の相違によって利潤も異なる
- 表3 資本構成の相違によって生産部門ごとに利潤率が異なる
- 表4 資本移動の結果,各部門での供給量が変化し,価格が変動する
- 表5 価格変動による需要の変化が生じて,全部門の利潤率が均等になった
- 表6 均衡状態ではどの生産部門の商品も生産価格で販売される
- 図208 平均利潤は総剰余価値を資本量に応じて分配したものである
- 図209 資本の有機的構成の高度化にともなう利潤率の低下
- 図210 剰余価値率の上昇は新価値率(p'の上限)の低下を相殺できない
- 図211 利潤率の低下をもたらす諸要因と反対に作用する諸要因
- 図212 商業資本の自立化とその運動
- 図213 商業利潤の源泉としての売買価格差(販売価格-購買価格>0)
- 図214 商業資本家は商品を,その価値よりも安く買って,その価値で売る
- 図215 商業資本の購買価格と販売価格
- 図216 商業資本の販売価格には商業費用がはいる
- 図217 産業資本の回転と商業資本の回転との相違
- 図218 再生産過程の内的関連と商業資本の運動の外的な自立性
- 図219 生産関係の発展と物神性の発展
- 図220 貨幣取扱資本のもとへの貨幣の集中とそのもとでの遊休貨幣の形成
- 図221 貨幣取扱資本のもとでの遊休貨幣の利子生み資本への転化
- 図222 銀行資本(貨幣取扱業務および利子生み資本管理業務を営む資本)
- 図223 利子生み資本の媒介者としての銀行
- 図224 銀行制度の二つの側面と信用システムの二つの構成部分
- 図225 銀行資本の利潤
- 図226 貸借対照表と損益計算書
- 図227 銀行の貸借対照表と損益計算書
- 図228 土地所有の制限によって生じる超過利潤の絶対地代への転化
- 図229 土地条件から生じる超過利潤の差額地代への転化
- 図230 資本主義的生産様式における諸収入とそれらの真の源泉
- 図231 社会的総生産物の二つの価値構成部分と新価値の分解
- 図232 国民総生産と国民所得
- 図233 国民所得と資本主義社会の諸階級へのその分配 ⇒巻末折込み
- 図234 経済的三位一体の定式
- 図235 資本主義社会の基本的階級関係
- 著者
-
大谷禎之介(おおたに・ていのすけ)
1934年,東京都に生まれる。
著訳書
1957年,立教大学経済学部卒業,大学院経済学研究科に進む。
1962年,東洋大学経済学部助手。同専任講師,助教授を経て,
1974年から,法政大学経済学部教授。経済学博士(立教大学)。
1992年から,国際マルクス=エンゲルス財団編集委員。
1998年-2015年,同財団日本MEGA編集委員会代表。
2005年から,法政大学名誉教授。- マルクス『資本論草稿集』全9巻,(大月書店(共訳),1978~1994年)
- マルクス『資本論の流通過程』(大月書店(共訳),1982年)
- 『ソ連の「社会主義」とは何だったのか』(大月書店(共編著),1996年)
- チャトバディアイ『ソ連国家資本主義論』(大月書店(共訳),1999年)
- 『図解 社会経済学:資本主義とはどのような社会システムか』(桜井書店,2001年)
- 『マルクスに拠ってマルクスを編む』(大月書店,2003年)
- 『21世紀とマルクス』(桜井書店(編著),2007年)
- MEGA②II/11:Manuskripte zum zweiten Buch des "Kapitals" 1868 bis 1881.((共編)Akademie-Verlag,2008年)
- モスト原著,マルクス改訂『マルクス自身の手による資本論入門』(大月書店(編訳),2009年)
- マルクスのアソシエーション論:未来社会は資本主義のなかに見えている(桜井書店,2011年)
- 『マルクス抜粋ノートからマルクスを読む』(桜井書店(共編著),2013年)
- 『マルクスの利子生み資本論』』全4巻,桜井書店,2016年
- A Guide to Marxian Political Economy: What Kind of a Social System Is Capitalism, Springer International Publishing AG, 2016
- 資本論草稿にマルクスの苦闘を読む,桜井書店,2018年