日本経済がわかる 経済学 菊本義治,宮本順介,本田 豊,間宮賢一,安田俊一,伊藤国彦,阿部太郎著
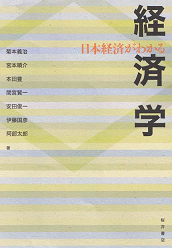
大学の授業現場から生まれた新しいスタイルの経済学入門
経済学を役立てるとは
- A5判/上製/288頁
- ISBN978-4-921190-44-6
- 本体2800円+税
- 初刷:2007年10月10日
- 第2刷:2008年3月25日
- 第3刷:2009年4月25日
- 第4刷:2010年3月30日
編者の言葉
目次
第3篇 信用制度下の利子生み資本
- 経済学の基礎知識
-
第1部 ミクロ経済学
-
第1章 企 業
- 1 企業のしくみ
- 2 企業の諸決定
- 3 企業の目的
- 4 コーポレート・ガバナンス
- 5 社会関係としての企業
-
第2章 家 計
- 1 家計の概念
- 2 家計の所得と消費
- 3 家計の貯蓄
- 4 生 活
-
第3章 政 府
- 1 政府の組織
- 2 政府の規模
- 3 政府の役割
- 4 政府の財源
-
第4章 金融機関
- 1 金融のしくみ
- 2 金融機関
- 3 銀行の目的と機能
-
第5章 市 場
- 1 市場原理
- 2 市場メカニズムの限界
- 3 市場原理の成果
- 4 市場原理主義
-
第1章 企 業
-
第2部 マクロ経済学
-
第1章 国民経済計算:利潤決定式
- 1 生産活動の量的測定
- 2 GDPの限界
-
第2章 生産・雇用の決定
- 1 新古典派の雇用理論
- 2 ケインズの雇用理論
- 3 2つの理論の統合
-
第3章 需要分析
- 1 さまざまな需要
- 2 乗 数
-
第4章 貨幣と金融
- 1 貨幣とはなにか
- 2 貨幣量
- 3 貨幣の供給
- 4 貨幣の需要
- 5 金利の決定
-
第5章 政 策
- 1 経済政策の手段
- 2 経済政策の効果と限界
- 3 平成不況における経済政策
-
第6章 貿易と資本移動
- 1 国際収支
- 2 貿 易
- 3 資本収支
- 4 為替レートの決定
- 5 多国籍企業
-
第7章 成長と循環
- 1 経済動態と投資
- 2 景気循環
- 3 経済成長
-
第1章 国民経済計算:利潤決定式
- 日本経済
-
第3部 戦後日本経済の推移
-
第1章 戦後復興期(1945年〜1955年)
- 1 戦前の日本経済
- 2 傾斜生産方式
- 3 経済民主化政策
- 4 高度成長への道
-
第2章 高度成長期(1956年〜1973年)
- 1 高度成長期における経済成長率と寄与度
- 2 高度成長実現の要因
- 3 民間設備投資拡大と期待成長率の高まり
- 4 旺盛な公共投資
- 5 「国際収支の天井」の克服
- 6 高度成長の矛盾と破綻
-
第3章 高度成長破綻後の調整期(1974年〜1991年)
- 1 「調整期」における経済成長の特徴
- 2 「調整期」における経済動向の推移
-
第4章 長期不況期(1992年〜現在)
- 1 長期不況期の経済実態
- 2 小泉「構造改革」とその矛盾
-
第5章 経済成長と企業の利潤率
- 1 企業の利潤率維持の意義
- 2 利潤率の決定
- 3 戦後日本経済の利潤率の動向
-
第1章 戦後復興期(1945年〜1955年)
-
第4部 現在の諸問題
-
第1章 長期不況
- 1 長期不況と企業行動
- 2 経済成長と日本経済
-
第2章 雇用問題
- 1 大競争時代と雇用の流動化
- 2 雇用環境とマクロ経済
-
第3章 企業の変容
- 1 日本型企業
- 2 日本型企業の特徴
- 3 日本型企業の変容
-
第4章 財政再建
- 1 財政危機の現状と財政再建の重要性
- 2 中長期財政試算の分析フレームワーク
- 3 政府の財政再建政策の基本戦略
- 4 財政再建に関する政策シミュレーション
-
第5章 少子・高齢社会と社会保障
- 1 日本の将来人口の見通しと社会保障の課題
- 2 老後生活保障の根幹としての公的年金制度設計に向けて
- 3 財政バランス優先の医療・介護制度からの脱却と公費負担の重要性
- 4 少子化対策の切り札としての福祉優先の社会経済システム構築
-
第6章 金融再編
- 1 日本型の金融システム
- 2 金融再編の第1段階
- 3 日本版ビッグバン
- 4 不良債権処理から金融機関再編へ
-
第7章 資金市場
- 1 1500兆円の家計金融資産
- 2 部門別資金過不足の推移
- 3 資金フローの金融仲介ルート
- 4 証券(株式)市場
- 5 金融派生商品市場
- 6 国際的な資金の流れ
-
第8章 企業の多国籍化と経済のグローバル化
- 1 日本企業の多国籍化
- 2 経済のグローバル化
- 3 グローバリズムの問題点
-
第9章 格差社会
- 1 格差拡大の実情
- 2 人口構成の変化と格差拡大
- 3 格差社会の根本原因
- 4 格差社会肯定論
-
第10章 日本経済の選択
- 1 日本経済の現局面
- 2 マネーゲームか、ものづくりか
- 3 高貯蓄型経済か、国民生活重視型経済か
-
第1章 長期不況
- 参考文献
- 索引
著者紹介 ( )内は専攻
- 菊本義治 1941年生まれ、大阪経済大学教授・兵庫県立大学名誉教授(理論経済学)
- 宮本順介 1950年生まれ、松山大学経済学部教授(理論経済学)
- 本田 豊 1951年生まれ、立命館大学政策科学部教授(日本経済論・計量経済学)
- 間宮賢一 1954年生まれ、松山大学経済学部教授(理論経済学)
- 安田俊一 1961年生まれ、松山大学経済学部教授(理論経済学)
- 伊藤国彦 1961年生まれ、兵庫県立大学准教授(国際金融論)
- 阿部太郎 1974年生まれ、名古屋学院大学経済学部講師(マクロ経済学)

学生から、「経済学は役に立ちますか」とよく聞かれる。その意味が「お金をもうける」ということであれば、経済学は必ずしも役に立たない。しかし、現実経済の理解と問題解決についてであれば、「役に立つ」と答えることにしている。
そのように答えながら、いつも何か違和感をもたざるをえない。ミクロ経済学やマクロ経済学を教えていて、果たして現実と切り結んでいるだろうかと不安になる。むしろ無力さを感じることがある。
部分的な現象の羅列では科学とはいえない。経済学、ミクロ経済学とマクロ経済学は現実経済を理論的に理解できるための基礎概念と分析方法の体系でなくてはならない。私たちが暮らしている経済社会について理論的・体系的に説明できなくてはならない。現在の経済理論は数学的に洗練され、精緻な魅力的な体系になっている。しかしながら、経済学は現実経済の理解と問題解決にどれだけ役立っているだろうか。
ミクロ経済学は経済主体者の合理性の体系化であることから、各経済主体者の主観的願望をのべる部分・主体均衡である。経済現象は人間行動によって生じたものであるから人間行動の合理性を追求することはだいじであるが、人間行動は合理性だけでは説明できない側面を持っている。また、個人の主観的願望だけではなく、集団としての、組織としての行動を分析しなければ、経済主体者の行動分析にはならないことが多々ある。
現在のマクロ経済学はミクロファンデーションを重視するあまり応用ミクロ経済学になっている。マクロ経済学は個々の人間行動の足し算ではない。主観的な願望や意図を超えて客観的に成立する現象が分析対象である。
アカデミズムとしての経済学や経済学界においては、それ独自の課題があり、一見「現実離れしたパズル遊び」も行わなければならないが、それも現実とまったくかけ離れた問題を取り扱っているわけではない。必ず現実のある側面を取り扱っているのである。ましてや、職業として経済学を学ぶのではない人々にとっては、経済学は現実の経済を理解するためのものであり、それを指針として実社会を生きていくのであるから、現実とのかかわりが強く求められるのである。
経済学とはなにか。古来、いろいろな答えがある。ある人は「経世(国)済民」だという。それは、国の富を増やし国民生活をよくすることである。Economyとは語源的にはギリシャ語のOikonomiaであり、Oikoとはhouseだが、それは単に住宅ではなく生活環境(Environment、EcologyのEcoにも通じる)である。Nomiaはmanage(管理する)である。つまり自然の摂理を理解し、生活環境をうまくコントロールして、自分たちにとって良い状況をつくること、人々の幸せを実現することである。また、Economyとは節約、すなわち目的を最小限の費用で実現するための効率性の追及だという意見もある。これも単なる費用・効果論ではなく、効率的な生産活動によって人間の物質的・精神的な豊かさを実現する条件をつくることだと解釈できる。
このように経済学のどの定義から見ても人間の幸せと関係している。これをもっとも表している言葉が福祉である。福祉とはWelfareであり、幸せという意味である。幸福追求である。経済学は幸せをどうすれば実現できるか、逆に言えば、なぜ幸せになれないのかを明らかにすることである。
これまで、経済学者たちは国民の幸福のために一国の富と分配に関して研究してきた。現在では、一国だけでは不十分であり、世界的な観点、人類の観点がだいじであるが、幸せに暮らしていける条件を研究することが経済学の課題といえよう。現実経済との切り結び、国民生活の安定と向上ための政策提言が求められているのである。
本書の問題意識は、現実の日本経済を理解するうえで現在の経済理論はどれだけ有効性を持っているかを明らかにすることである。この課題を達成するためには、執筆者がどれだけ経済学に習熟しているかが鍵となる。己の理解力不足を経済学の責任にするわけにはいかない。この点の評価は読者にゆだねるほかない。
本書では日本経済を理解するうえで必要と思われるミクロ経済学とマクロ経済学の理論を第1部と第2部で述べている。学問的には面白いけれども、日本経済の理解には必ずしも必要ないと思われる点については思い切って捨象した。そして、第3部で第2次世界大戦後の日本経済の推移を述べている。その際、現在の日本経済が資本主義経済であること、資本主義経済は利潤獲得を目的としていることから、利潤がどのような要因によって決められるかを分析の基本視点とし、第3部第5章などで詳しく述べている。
第4部において現在問われている重要問題を取り上げた。そこでの課題は、第1部から第3部で学んだ知識を用いて日本経済をどれだけ科学的・理論的に理解できるかである。私たちは経済学が現実理解に有益である、という見解をもっている。第4部が理論的に説明できているかどうかが本書の生命線といえよう。(本書「まえがき」より)